産業・経済
-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
花王の紙おむつ「メリーズ」人気が中国で過熱
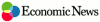
花王<4452>の紙おむつ「メリーズ」がアジアで人気を集めている。特に中国での人気が過熱している。中国の紙おむつ市場では、米P&Gやユニ・チャーム〈8113〉が先行していたが、花王は2009年からメリーズの輸出を開始、13年からは現地生産も始め、急速に追い上げている。
メリーズ人気の理由は、「モレない・ムレない」のキャッチコピーの通り、その高い通気性と柔らかさによって、「赤ちゃんの肌に優しい」と高く評価されているからだ。例えば14年8月に新発売された「メリーズパンツ さらさらエアスルー」。Mサイズには、パンツの内側に「ふんわりエアリーメッシュシート」が採用されている。花王では、ふわふわの凹凸加工により、点と点で肌に触れ空気が通り抜けるため、これまでの商品よりもおよそ3倍の通気性が期待できるとしている。
中国では、中国製の安全性に対する信頼が揺らぐ中で、「日本製は安心」というイメージが定着し、メリーズ人気が加速している。同国では富裕層の間でその需要が拡大し、昨年半ばごろから、メリーズの品薄が常態化している。そのため、倍以上の値段で取引されるという状況にもなった。
中国人ブローカーが日本国内でメリーズを買い占め、中国に持ち込んで高値で売るという事態にまで至った。昨年10月には、兵庫県警が、中国籍の男3人がメリーズを買い占める仕事に従事していたとして、出入国管理法違反(資格外活動)の容疑で逮捕した。3人は調理師の在留資格で入国しながら、神戸、明石、姫路各市のドラッグストアでメリーズなどの紙おむつを買い占めていた。兵庫県警によると、3人は延べ270店から、メリーズを中心とした紙おむつ990パックを購入していた。
メリーズは、中国のほか、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシアなどで販売され、高い評価を得ている。14年にはベトナムでの販売も開始、さらに同年には、西ジャワ州のカラワン工業団地にインドネシアの第二工場を新設し、メリーズの生産を開始している。アジアにおける日本製紙おむつの販売は、今後さらに拡大していきそうだ。(編集担当:久保田雄城)
PR -
iPhoneのロック画面からクイズに参加できるアプリ「STREAK」


「STREAK」はiPhoneのロック画面からクイズに参加できるアプリです。Notificationで◯×クイズが送られてきて、スワイプすると「True」「False」で回答することができます。1回まで間違えることが可能で、何問正解できるかを競うゲームです。 以下に使ってみた様子を載せておきます。
まずSTREAKへアクセスしましょう。アプリをインストールして、通知を許可します。クイズ開始まで時間がある場合は、練習モードですぐ試すことができます。

このようにNotificationでクイズの本文が送られてきます。左にスワイプして、◯か×かを回答しましょう。しばらくすると結果が返ってきますよ。何問正解できるかチャレンジできます。ロック画面から参加できるのでとても気軽に行えます。ぜひ一度挑戦してみてはいかがでしょうか。
STREAK
(カメきち)
元の記事を読む
-
熱く胎動するASEAN市場 日本企業の進出も活発に
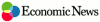
2015年12月の発足に向け、いよいよ秒読み段階に入ったASEAN経済共同体(AEC)。現在のところ、EUのような通貨統合の動きこそないものの、域内の関税撤廃や幹線道路などのインフラ整備など、市場統合に向けたも準備は着々と進んでいるようだ。
タイやインドネシアなど東南アジアの10カ国が加盟する人口6億人の巨大市場は、5億人の欧州連合(EU)の市場規模を大きく上回る。当然、世界の経済に及ぼす影響は計り知れない。日本も、とくに自動車や製造業などの企業の生産や販売戦略は大きな転換期を迎えることになるだろう。
そんな中、ASEAN統合をにらんで、日本企業のASEAN市場への進出も相次いでいる。例えば14年7月には、KDDI<9433>と住友商事<8053>がミャンマー連邦共和国の通信事業への参入を発表している。両社はミャンマーの独占的な国営通信事業者MPT社との共同事業運営契約を締結し、10年間で約2000億円の設備投資を実施する。現在、ミャンマーの携帯普及率は10%強と見られているが、通信インフラや電力インフラが整えば爆発的な市場拡大も見込まれる。
また、バンダイナムコ<7832>は、アジアでの事業拡大・強化に向けてインドネシアに現地法人「PT BANDAI NAMCO INDONESIA」を設立し、14年10月より営業を開始している。ここを拠点とし、インドネシアでの製造・販売による同国での玩具事業拡大を図るだけでなく、ASEAN輸出事業を積極展開していく方針だ。
また、消費税引き上げ影響などで国内市場が不安定な住宅業界でも、新たな市場を求め、日本の住宅会社のASEAN市場への進出が活発になっている。対象地域としては、これまでタイやベトナムが中心だったが、今年に入って大手のパナホーム<1924>が、4月1日付でシンガポールに同社100%出資による新会社「パナホーム アジアパシフィック」を設立することを発表、マレーシアを除くASEAN地域での住宅事業拡大に本格的に乗り出したことで大きな注目を集めている。
シンガポールはASEAN各国から概ね2時間程度で移動可能な好立地。ここに統括会社を置くことで、情報収集や営業活動を行うとともに、地元ディベロッパーとSPC(特別目的会社)を設置し、案件毎に建設体制を組織する等、地域主導型の受注・建設体制を構築し、ASEAN市場を一気に掌握するのがパナホームの狙いだ。…
-
国連防災世界会議」行政と民間企業の防災の取り組みに世界が注目

仙台市で3月14日から18日まで、「第3回国連防災世界会議」が開催され、世界186の国と地域から6500人、のべ15万6千人を超える参加者が訪れた。 この会議のスタディツアー(被災地公式視察)にも海外より多くのゲストが参加。津波で被災した小学校の校舎や農業の復興への取組み、沿岸部での津波への備えなど26のツアーが実施された。
その一つ、官民連携の防災の取り組みとして注目された宮城県・色麻町と地元の積水ハウス<1928>東北工場のスタディツアーに筆者も参加した。5日間で24の国と地域から約200人が視察に訪れたという。
積水ハウスは2013年9月に同工場のある宮城県・色麻町と「防災協定」を締結した。また14年5月に、積水ハウスのオーナーや地域社会への安全や安心を提供することを目的に各地の工場の防災力を高める「防災未来工場化計画」を発表している。
同工場では、「スマートエネルギーシステム」を構築。700キロワット(一般家庭の約233世帯分)のメガソーラーやエネルギー管理システム(FEMS)を導入し、平時には地域の電力ピークカットに貢献しながら、エネルギー使用量削減につなげているという。これらと大容量の蓄電池や発電機を組み合わせ、災害時のエネルギー供給を可能にしている。ツアーでは、このエネルギーシステムの他、非常時に250人が7日間生活できる避難所として活用する体験型施設「住まいの夢工場」や、食料や水などの防災備蓄品などが紹介された。災害時に民間の施設が地域社会の人々のサポートをするというわけだ。
14年10月には、色麻町と同社は合同で町の災害対策本部を同工場内に設置することを想定した防災訓練を行った。「スマートエネルギーシステム」によって確保したエネルギーを災害対策本部や避難所で利用。さらに、プラグインハイブリッド車を、災害時の電力供給源として、初動対応時の移動手段として活用するという。また色麻町は、高速無線通信「地域WIMAX」を活用した「災害に強い情報連携システム」を構築しており、積水ハウスとの合同防災訓練で、被災状況などの確認に活用し、その有効性を確認したという。
伊藤拓哉 色麻町長は、「町と民間企業の連携は住民にとって大きな安心につながっている。」と語り、阿部俊則 積水ハウス社長は「防災は住民と行政、企業との関わりが大切。命を守るシェルターでもある住宅の重要な役割を外国の方にもお伝えしたい。…
-
三洋電機が事実上の消滅
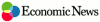
パナソニック<6752>が傘下の三洋電気の子会社である三洋テクノソリューションズ鳥取を3月中にも国内の投資ファンドへ売却する方針を固めたことがわかった。この三洋テクノソリューションズ鳥取は、三洋電気が直轄している最後の電子機器生産の事業であり、売却されることにより、三洋電機は事実上消滅することになる。ただ、三洋電気の法人格は引き続き維持される。約10万人だった三洋電気社員も、現在は約200人しか残っておらず、早期退職を募っている他、パナソニックおよびパナソニックグループ会社へ4月1日に移籍となる予定である。
三洋電機はGHQの公職追放令により松下電器を退いた、松下幸之助の義弟である井植歳男が1947年2月1日に、三洋電気製作所として創業。49年4月1日に三洋電気株式会社設立した。当初は自転車用発電ランプ「ナショナル発電ランプ」、昭和の三種の神器の一角となる洗濯機に着目し国内のシェアトップを誇った。リチウムイオン電池の世界シェア23%を持ち、超軽量アモルファス太陽電池を動力源としたソーラープレーンによる北米大陸横断に成功するなど、高い技術力が評価されていた。
転機となったのが2005年に起きた新潟県中越地震により子会社が被災したことだ。500億円を超える損失を計上。同年11月総合家電メーカーから撤退し、リチウムイオン電池やニッケル水素電池などの2次電池や太陽電池を中心として事業の立て直しを図る。08年11月7日パナソニックが三洋電気を子会社化。パナソニックもリチウムイオン電池の世界的なシェアを8%持っており、両社が統合されることで米国のニッケル水素電池の売り上げをほぼ独占できるはずであった。だが、独占禁止法の審査に手間取り、この間、円高や中国・韓国といった新規の電機メーカーの台頭で三洋電機の米国での競争力が低下することとなり負債のみが残った。
その結果、パナソニックと重複する事業はすべて売却。現在、三洋電気は三洋テクノソリューションズ鳥取が残るのみとなった。3月に三洋電気は事実上消滅をするが、その技術や事業は現在経営再建中であるパナソニックの重要な要素となるはずである。(編集担当:久保田雄城)
