産業・経済
-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
OZONEシンポジウムから考える、住まいのかたちと変化、未来

この20年、私たちは見えないものも『かたち』と呼ぶようになった
西新宿にリビングデザインセンターOZONEがオープンしたのは1994年。ウェブブラウザーが登場、短期間に圧倒的なシェアを獲得したのと同じ年で、インターネット検索が日常になり始めたタイミングだったともいえる。それから20年、インターネットは私たちの生活に欠かせない存在となり、生活のあり方、人間関係、住まいとのかかわり方など多くのものを変えてきた。その20年を振り返り、今後の住まいとそれに関わるプロのあり方を考えるシンポジウム「住まいのかたちにプロは要るのか? ~住宅の価値をあらためて考える~」が行われた。ここではそのエッセンスをご紹介しよう。
シンポジウムはファシリテーターと3人の登壇者によるプレゼンテーションで始まった。最初のプレゼンテーションはファシリテーターでもある建築史家の倉方俊輔さんから。テーマはシンポジウムのタイトルである、住まいのかたち、そしてプロという存在について。倉方さんはそのいずれもがこの20年で大きく変容したという。
「今、私たちはたとえばシェアをデザインするなど、有形でないものについても『かたち』という言葉を使うようになっています。これは『かたち』という言葉の認識そのものが変化したことを示しています。かっこいい形が「建築」である、といったような理解は乗り越えられ始めているでしょう。では、これからの「建築らしさ」とはなにかということが問題になります。
もうひとつ、20年前には情報、ノウハウを持ったプロが明確に存在していました。しかし、今は分野によっては建築家よりも詳しいアマチュアがいるなど、情報、技術の進化がプロとアマの差を詰めてきている。その結果、見える形だけを作るのならアマでもできるのかもしれないという状況になってきています。また、当初デジタルは物事を平準化すると言われていましたが、実際には場所の特性が際立つようになるなど、微細な差異がクローズアップされるようになってきています。そうした状況下で住まいにプロは必要なのか、根源的な要不要も含め、考えたいと思います」。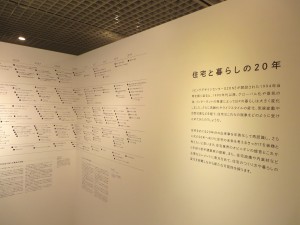
ITの普及は社会も、住宅も、住み方に対する考え方をも変えつつある
『かたち』の変容については最後にプレゼンテーションをした日本版『WIRED』編集長の若林恵さんの話と重なる部分が多かったのが印象的だった。今回のシンポジウムの登壇者は倉方さんに始まり、HOME’S総研所長の島原万丈さん、建築家の松川昌平さんと建築、不動産の専門家だが、若林さんは未来に繋がるアイディア、イノベーション、テクノロジーなどを紹介するメディアの人で、言ってみれば異分野からの参加。…
PR -
横浜のベテラン二階建てバス、引退へ 長寿の理由はその「生まれ」

横浜市交通局で唯一の二階建てバスが、2015年3月末をもって引退します。実はこの車両、通常なら法規制で12年しか使えない神奈川で、20年以上も活躍しました。なぜそれほど長く走ることができたのでしょうか。「生まれ」にその理由がありました。
12年しか使えない神奈川で21年走行
横浜市交通局から、2015年3月末をもって二階建てバスが姿を消すことになりました。1984(昭和59)年から横浜市交通局は二階建てバスを導入しており、今回姿を消すのは1994(平成6)年に導入された2代目の、「ヨンケーレ・モナコ」と呼ばれる車両です。
かつて横浜市交通局の二階建てバスは観光周遊バス「ブルーライン」として横浜市内の観光地を巡回していましたが、1980年代を中心に起こった「二階建てバスブーム」の収束や、経由地だったベイブリッジ人気の低迷から運行を終了。以降は定期観光バス「横濱ベイサイドライン」として活躍したものの、現在は二階建てではない車両に役目を譲り、1台が予備車両として残るのみになっていました。
さて、それにしても横浜市交通局が1984年に初めて導入した二階建てバスは約10年の活躍でしたが、2代目の「ヨンケーレ・モナコ」は1994年から21年もの活躍です。同じ事業者の車両ながら、なぜここまで2代目は在籍期間が長くなったのでしょうか。
特にディーゼル車が主役のバスは、「自動車NOx・PM法」という法律で使用期限などの規制が地域によって存在。神奈川県内では1994年が初年度登録だった場合、12年しか使用できません。にもかかわらず、です。
法規制を受けない理由はその「出生」に
横浜市交通局の「ヨンケーレ・モナコ」がそうした規制に影響されず21年も活躍できた理由は、「輸入車」だからです。この車両はベルギーのバス車体メーカーであるヨンケーレが、日産ディーゼル(現「UDトラックス」)のシャーシと組み合わせて製造した「モナコ」というモデル。それを日本に輸入した形です。
一般的に日本国内で生産された自動車は、「型式認定」という審査を国土交通省から受けて合格したのち市販されます。そしてこの際、排ガス規制についても認定が行われ、車検証へ合わせて記載されます。
しかし国内で製造されていない輸入車はこの「型式認定」を受ける必要がなく、「型式不明」として登録されます(車検証には便宜上の型式が記載され、この「ヨンケーレ・モナコ」は「RG620VBN」)。…
-
尾道松江線が全線開通=中国横断道、地元で式典-広島

中国横断自動車道尾道松江線の開通式典で、同線の愛称「中国やまなみ街道」のデザイン看板の除幕を行う関係自治体の首長ら=22日午前、広島県三次市
松江市と広島県尾道市を結ぶ中国横断自動車道尾道松江線(中国やまなみ街道)が22日、全線開通する。同日午前には同県三次市のホールで開通式典が開かれた。今回開通するのは残っていた世羅インターチェンジ(IC、広島県世羅町)-吉舎IC(三次市)間20.4キロ。一般の供用開始は午後5時から。
同線は全長137キロ、総事業費約4242億円で、1993年度に日本道路公団が整備を開始した。その後、小泉政権下の公団改革の過程で事業見直しの対象となったが、最終的に全区間の8割以上で事業費の4分の1を地元が負担する新直轄方式が採用され、開通にこぎ着けた。 -
外食産業戦国時代の勝ち組「吉野家・ココイチ・魚べい」はここが違う!

■外食業界、戦国時代。吉野家・ココイチにみる成功するための経営戦略
外食産業の勝ち負けがはっきりしてきた。報道の通り、安売り路線であるマクドナルドHD <2702> が赤字転落する一方、カレーチェーン「ココイチ」を経営する壱番屋<7630>、吉野家HD <9681> は増収となった。明暗が分かれる外食業界の成功要因は何だろうか?各社の業績と戦略から成功の鍵を探っていく。
■1.安売り系は客数減による売上高減へ
まず、外食産業の基本指標である客数と客単価を見ることで、安売り系の外食チェーンがどんな状況に置かれているのかを見て行きたい。
安売り系のチェーンは消費税が増税された2014年4月以降、客数減の悪循環にはまるり業績が転落している。例えば、マクドナルドHDの客数は、2013年4月~2015年2月の23ヶ月連続で前年同月比マイナスとなった。
特に、中国産鶏肉の品質問題が発覚した2014年8月以降は2015年2月まで7ヶ月連続で2桁の前年同月比マイナスとなった。
客単価で見れば、2014年6月まで前年同月比増をキープし、中国産鶏肉の品質問題発覚後の2014年11月も前年同月比―0.4%とほぼ横ばいをキープしているので、マクドナルドHDの業績悪化の主因は客数の減少である。
また、ゼンショーHDの客数も、2014年4月以降は5月と7月を除いて前年同月比マイナスであり、特に9月以降で見ると前年比91.7%と1割近いマイナスとなっている。ゼンショーHDの客単価は前年同月比増をキープしているが、客数の落ち込みが主因で、2015年3月期の売上高は前年比94.5%にとどまっている。
このように、安売り系の外食チェーンにおいては、客単価はそれほど減少していないにもかかわらず、客数の減少により売上高が減少している。客数減少の要因としては、マクドナルドHDは中国産鶏肉の品質問題がうまくいかず、深夜営業を取りやめたことである。オペレーションの品質維持が客数維持のためには重要だとといえる。
■2.客数増が好調な業績を牽引
壱番屋及び吉野家HDの客数と客単価の推移は、マクドナルドHDとは対照的だ。
壱番屋の客数は平成25年10月以降、17箇月連続で前年同月比増となっており、客単価も平成25年12月以降、15ヶ月連続で前年同月比増となっている。
ただし、今期の客数の前年同月比比率は105.0%であるのに対し、客単価は101.3%であり、壱番屋の好調な業績を牽引しているのは客数増である。… -
【ギョーカイ先走り03】トヨタ86にセダンはなぜ出てこないのか?? オープンは???

久々のFRスポーツとして登場したトヨタ86&スバルBRZ。発売から4年が経過し、来年にはビッグマイナーチェンジの実施が予定されています。スバル流の年次改良もあって、少しずつ、しかし確実に熟成されていて、スポーツカーの命であるハンドリングもしっかりとレベルアップしています。
このFRのプラットフォームを生かして、他のボディを与えて、新たなスポーツカーファミリーが誕生するのではないか、というウワサもありました。4ドアセダンやスポーツワゴン、そしてSUVなど、86&BRZのスポーティなハンドリングを受け継いだ発展形が期待されていたのです。しかし未だに、そうしたボディは登場していません。
もっとも注目されていたのは86&BRZセダンだったと思います。スポーツカーをベースにした、ホンモノのスポーツセダンというコンセプトになります。4ドアボディで快適に4人が乗れるスペースがあれば、もっと多くの人がFRスポーツを楽しむことを考えるようになるかもしれません。
しかし現実には困難な部分が多かったようです。
まずリヤシートのスペースを拡大するためには、ホイールベースを伸ばさなければなりません。低重心の追求を徹底的にやってきた86&BRZは、低いポジションが与えられていて、スペースを得るには、より長いホイールベースが必要になります。ホイールベースが伸びれば当然ボディは長くなり、それは車両重量を増やしてしまいます。
軽量であるというのも86&BRZの生命線ともいえます。重くなってしまうとエンジンパワーを上げなければならなくなります。排気量を2.5Lにするか、あるいはターボを搭載するのか?? どちらにしても86&BRZから離れていってしまいます。
ホイールベースを伸ばせば、ハンドリングにも影響が出てしまうので、少しボディを高くしてスペースを捻出しましょうか。低重心という設計思想が少し薄くなってしまいますが、リヤシートの快適性は大きく向上することでしょう。
しかし、やればやるほど、スバルWRXに近づいていってしまうような気がしませんか??スポーツカーにはスポーツカーの流儀があります。古くからスポーツカーには、発展型のボディがあります。それが2ドアのスポーツワゴン、シューティングブレークというスタイルです。
フロント部分からドアまでのボディはそのまま流用して、ボディ後半を作り直すことで作ります。…
