社会
-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
飲食業界で重宝される外国人留学生 採用担当者「何を吸収して母国に帰るのかを見ている」


人材不足が叫ばれている飲食業界で今、外国人労働者の採用に力を入れる企業が増えている。厚生労働省が2014年10月に発表したデータによると、日本で働く外国人労働者は過去最多の78万7627人。業界からは「外国人の方がある意味真面目に、目的意識がしっかりしているため、これから核になる人材だ」という声も出ている。
3月16日に放送された「とくダネ!」(フジテレビ系)では、外国人アルバイトの面接現場を紹介し、採用から実際に働くに至るまでの外国人労働者の様子に密着していた。
■問題はやる気。使う言葉は少なく「慣れ」で乗り切る
お台場のラーメン店で面接をしていたのは、日本語が片言のネパール人の男性。メニューの中にある「赤」という漢字が分かるかとの問いに、「ちょっと分かります」と言うものの、書いてみてと言われると実際には書けない。
しかし、そこでめげることなく「でも頑張ります。何でもやります」とガッツをアピール。男性の姿に、面接をしていた店長は採用を決めた。なぜ採用を決めたのかとの質問に、
「使う用語って慣れじゃないですか。普段の会話ってあまりないんで」
厨房の中ではあまり会話がないため、洗い物の担当なら問題ないという。
番組では、外国人アルバイトの採用に力を入れる「大阪王将」も紹介。採用担当者が日本語学校を訪れ、この日はアジア系の留学生を中心に11人の面接をしていた。
「日本語を喋ってもそんなに通じないと思っていて、我々のところで働いて、何を吸収して母国に帰るのかを見ている」
と語る採用担当者。面接では単純な日本語の語学力を見ているのではなく、応募した動機が重要だと考えているようだ。学生の中には、東大に行くことが夢だと語る男子学生や、日本に来てまだ1か月で全く会話が噛み合わない男子学生、志望動機を聞かれて突然「好きです」と言いだす女子学生もいた。
■日本人と同じ給与を支払う「大阪王将」
担当者が注目した学生は、経済の勉強をするため半年前に来日したネパールから来た20歳の女性。日本語の理解力は比較的高く、両親が母国でレストラン経営をしていることを話し、「私レストランの仕事できます」と滑らかな日本語で飲食店での経験をアピールしていた。
採用されたこの女性は、接客トレーニングで思わぬ苦労が待っていた。女性には、「失礼しまーす」「○○でございまーす」と語尾を伸ばしてしまう癖があった。
店長から何度も語尾を切るように指導されるものの、なかなか癖が直らない。…
PR -
子どもの教育費、中高生がもっとも高く月平均16,079円

子どもの携帯・スマホの通信・通話料金を支払っている親は52.3%にのぼり、平均支出額は7,558円であることが、ソニー生命保険が3月13日に発表した「子どもの教育資金と学資保険に関する調査」より明らかになった。
調査は2月15日~16日の2日間、大学生以下の子ども(複数いる場合は長子)がいる20~69歳の男女を対象に実施し、1,000人の有効サンプルを集計した。2014年1月に発表した調査に引き続き2回目となる。
子ども一人に対し、学校以外での教育費に1か月あたり平均でいくら支出しているか聞いたところ、平均9,757円であった。内訳は、「スポーツや芸術などの習い事」3,335円、「家庭学習費用(通信教育、書籍など)」2,424円、「教室学習費用(学習塾、英会話、そろばん教室など)」3,998円となっている。
子どもの就学段階別にみると、中高生が16,079円ともっとも平均支出額が高く、小学生(11,004円)、大学生(7,353円)、未就学児(4,528円)が続いた。内訳を比較すると、中高生の「教室学習費用」への平均支出額が9,506円と、ほかの層に比べて高く、高校受験や大学受験に向けた学習費がかかっているようだ。
子どもの携帯・スマホの通信・通話料金を支払っているか聞いたところ、「支払っている」52.3%、「支払っていない」47.7%。子どもの通信・通話料を支払っている人の平均支出額は7,558円となった。男女別に見ると、男子の親は7,947円、女子の親は7,184円で、男子の親のほうが支出額が高かった。
子どもの独立までにかかる教育資金の額について、「把握している」8.3%、「やや把握している」43.9%、「あまり把握していない」40.7%、「まったく把握していない」7.1%と、半数以上が把握していることがわかった。
未就学児の親(248人)に子どもが小学生から社会人になるまでに必要な教育資金はいくらくらいだと思うか聞いたところ、「1,000万円~1,400万円くらい」36.7%、「500万円~900万円くらい」14.1%、「2,000万円~2,400万円くらい」14.1%といった金額帯に回答が集まり、平均額は1,156万円となった。2014年調査の平均予想金額(1,229万円)と比較すると、73万円減少した。 -
<消滅可能性都市>上位100市町村、半数の首長選が無投票

民間の有識者会議「日本創成会議」の分科会(座長・増田寛也元総務相)が昨年推計した「消滅可能性都市」で、消滅可能性が高いとされた上位100の市町村のうち、過半数の52市町村で直近の首長選が無投票になっていたことが分かった。地方の衰退が、民主主義の基本である選挙にも影響を及ぼしている。
日本創成会議が示した消滅可能性都市(896自治体)のうち、「消滅可能性」の指標とされた20〜39歳の若年女性人口の減少率が大きい100市町村について、選挙結果を調べた。
首長選で無投票となった52市町村のうち、2回以上連続で無投票となっていたのは半数の26市町村。北海道の妹背牛町と津別町は5回連続で無投票だった。新人のみが立候補して当選した新人無投票も6町村あった。現職首長のうち17人は初当選から一度も選挙戦を経験せずに当選しており、選挙で民意を問う経験をしていない首長が多いことが浮き彫りになった。
100市町村の過去4回の選挙をさかのぼると、4回前の首長選では無投票率(市町村合併で新たにできた26自治体を除く)は38%だったが、3回前が44%、2回前が41%、前回は52%と無投票率が高まる傾向にある。4回連続で選挙戦になった自治体は11市町村にとどまった。総務省によると2013年に全国であった511の市区町村長選のうち、無投票は185で、無投票率は36.2%だった。
52市町村の都道府県別は北海道の16市町がトップ。青森5▽奈良4▽山形、和歌山3−−などが続き、東京都の1(檜原村)を含め23都道県に及ぶ。
無投票が続く市町村はいずれも高齢化や過疎化が深刻になっている地域が多い。にもかかわらず選挙戦が行われないことは、有権者が地域の問題を問う機会が失われていることを示す。地方の衰退が、人口だけではなく民主主義の基盤の揺らぎにもつながっている。
創成会議は、福島県内の市町村を除く全国1800市区町村(政令市の行政区を含む)で、子供を産む人の大多数を占める20〜39歳の女性人口が2040年までに5割以上減ると推計される896自治体を「消滅可能性都市」と位置付けた。「消滅可能性」1位だった群馬県南牧村は14年4月、2人が立候補して村長選が行われた。【小田中大】
◇自治力が低下
消滅可能性都市を指摘した増田寛也元総務相の話 消滅可能性都市で無投票が多いのは、自治力の低下を示すものだ。消滅の危機から解決策を出していく場合には、地域の自治力が大きく影響する。危機を乗り切るための方策は、住民の中でも大きく意見が分かれることがある。リーダーを選ぶ時には複数の候補者が大きな方向性をお互いに競い合わなければ、地域の活力が出てこない。無投票が続けば危機が人ごとになり、無力化や地域の沈滞化を招き、その地域がより消滅に近づくことになる。 -
「人殺す練習したかった」=中3逮捕、ヤギ襲撃で侵入―イスラム国影響か・警視庁
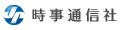
飼育されていたヤギを殺そうと小学校に侵入したとして、警視庁立川署は16日までに、建造物侵入容疑で、東京都立川市の同市立中学3年の男子生徒を逮捕した。男子生徒は「イスラム国の処刑映像を見て、人を殺そうと思った。その練習にヤギを殺そうと思った」などと供述しており、同署は男子生徒を東京家裁に送致した。
同署などによると、男子生徒は2月15日午前1〜2時ごろ、立川市内の市立小学校の正門を乗り越えて侵入した容疑で逮捕された。
校庭の小屋で飼育されていたヤギが騒いでいたため、自転車で近くをパトロール中の警察官が気付き、男子生徒を発見。逃走した男子生徒の身柄を確保した。生徒のリュックサックからバールと折りたたみ式ののこぎりが見つかったという。ヤギに被害はなかった。
男子生徒は不登校気味で、その後の捜査で、イスラム国の処刑映像などをインターネットで見ていたことがアクセス履歴から判明したという。
-
防衛官僚出身、安倍官邸の元参謀役が首相の無知を批判! 集団的自衛権はコスパが悪い

積極的平和主義などと称して「戦争のできる」国づくりへひた走る安倍晋三首相にとって、この人ほど”いなくなって欲しい”目の上のタンコブはいないだろう。柳澤協二氏、68歳。東大法学部卒で1970年に防衛庁(当時)入庁。審議官、局長、官房長などを歴任し、2004年4月から約5年半、小泉→安倍→麻生と3代の政権に渡って危機管理・安全保障担当の内閣官房副長官補として官邸の参謀役を務めたバリバリの元防衛官僚だ。この間に自衛隊のインド洋海上補給支援活動やイラク派遣などの立案にも携わった。テロと戦争のプロである。
そんな”左翼ではない”(というか身内だった)柳澤氏が、安倍政権の安保政策を徹底批判しているのだ。昨年4月に『亡国の安保政策――安倍政権と「積極的平和主義」の罠』(岩波書店)を出版したのを皮切りに、新聞・雑誌等のインタビューやテレビ出演はもちろん、全国各地を回っての講演会を精力的にこなしている。動機は、「かつて政府の中枢にいた人間の使命として、『おかしい』と思ったことは国民に伝えなければならない」からだという。今年1月には新著『亡国の集団的自衛権』(集英社新書)を出したばかりだ。
長年、日本の防衛の最前線で実務を担ってきた人だけに、その筆致は冷徹で異論を挟む余地がない。これを読むと、いま国会や与党協議で議論されている防衛論がいかに机上の空論であり、安倍首相の言う「積極的平和主義」が「空想的平和主義」なのかがよくわかる。
例えば、集団的自衛権が必要な根拠として、同盟国であるアメリカと中国の間で軍事衝突が起きたとき、中国に奇襲された米軍の艦艇を自衛隊が守らなくていいのかという主張があるが、そのためにいったいどれくらいの兵力が必要なのかの議論がまったくない。
柳澤氏の分析では、現状の4個護衛隊群では全然足りず、最低あと2個護衛隊群が必要となり、西太平洋までの距離の長さを考えれば、ミサイルや弾薬の備蓄もいまの数倍に増やさなければならないという。
さらに言えば、アメリカの船を守るために自衛隊を出したら肝心の日本の防衛が手薄になり、その分の補強も必要になる。いずれにせよ、大規模な軍備の増強と防衛費の増加が想定されるわけだが、財政的裏づけに関する話がいっさいない。ちなみに、備蓄増が必要な迎撃ミサイルだけでも1発数千万円もする。安倍首相は、集団的自衛権行使を認めればカネが湧いて出てくるとでも思っているのだろうか。…
