社会
-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
埼玉の男児死亡、死因は失血死 複数の傷も

さいたま市南区のマンション一室で1歳3カ月の木村映介ちゃんが刺され死亡した事件で、埼玉県警は21日、司法解剖の結果、死因は腹を刺されたことによる失血死とみられると明らかにした。刃物による傷は複数あったという。
県警は20日午後、映介ちゃんを包丁で刺したとして、殺人未遂の疑いで祖母の無職田中美栄容疑者(65)を逮捕。今後、容疑を殺人に切り替え、動機などを調べる。
県警によると、映介ちゃんは30代の母親と、一時的に田中容疑者宅で暮らしていた。外出していた母親が夕方帰宅し110番した。
PR -
インドネシア:GM撤退に追い込む、日本のミニバンの強さ 現地大臣“信頼している”

日本車のシェアが9割を超えるインドネシア。まさに「日本車天国」と言っても過言ではない状況である。2015年に入っても、日本車の異常なまでの強さは変わらず、日系メーカーの現地工場は増産・拡張・新設の一途である。
◆自動車市場のポジとネガ
現地メディアのムルデカ・ドットコムは、三菱自動車がジャカルタ郊外に新工場を建設する話題を報じている。「2014年の我が国の自動車市場は伸びを見せなかったが、それとは逆に三菱自動車は増産の道を進んでいる。(中略)この成果を背景に、同社はジャカルタ郊外カラワン工業団地に新工場を建設する。この工場は年間16万台の生産を目指す」
ちなみにこの16万台のうちの半分、8万台はミニバンになるという。燃費のいいミニバンは、インドネシアでは売れ筋の車種である。
この時点で「やはりインドネシアは景気のいい国だ。自動車がよく売れる」という感想を持つ読者もいるだろう。だが実は、三菱自動車はインドネシア自動車市場のポジの部分である。ポジには必ずネガがついている。そのネガとは、何と米自動車大手ゼネラル・モーターズ(GM)だ。
◆GMの「自殺行為」
ブカシ市のポンドック・ウングにあるGM完成車工場が、今年6月末までに閉鎖される。そこで働く約500人の従業員は解雇される予定だ。この話題については、現地紙シンドニュースの記事が「1995年に設立されたこの工場は、2005年にその生産が停止されていたものの、2013年5月に操業が再開されたという経歴を持つ」と伝えている。つまり、GMブカシ工場にとって今回の撤退は二度目の敗北ということである。なぜ、このような“天国と地獄”が出現してしまったのか。日本車の妖怪じみた強さについては、各メディアがそれぞれ分析している。
現地メディアのリマニュースは、「日本車の優勢が招いた、GMインドネシアの破綻。同社が目指していたシボレー・スピンを主力とするミニバン市場攻略は、まさに自殺行為であった」と非常に強い論調でGMの失策を論じている。
GMが手がけるシボレー・スピンは、2012年から製造販売されているミニバンである。ブカシ工場で生産が始まったのは2013年。だが、その販売台数は一向に振るわなかった。
同メディアは、「スピンの販売台数は、同社の生産キャパシティーの半分にも届かなかった。2014年にブカシ工場で生産されたスピンは約4万台、同年の国内販売はそのうちの8412台に過ぎない。…
-
<春一番>関東3年ぶり吹かず

春分の日の21日、関東地方は晴れたり曇ったりの穏やかな天気で強い風は吹かず、3年ぶりに春一番のない年となった。
春一番は、毎年2月4日ごろの「立春」から春分の日の間に最初に吹く南寄りの強風。気象庁によると、関東地方で春一番が吹かなかったのは、統計を取り始めた1951年以降で10回目という。21日の最高気温は東京都心で16.0度、横浜市で13.0度と平年並みだった。【日野行介】 -
<内閣府調査>「アベノミクス」恩恵実感できず

内閣府は21日、「社会意識に関する世論調査」の結果を発表した。現在の日本の状況について「悪い方向に向かっている」と思う分野を複数回答で尋ねたところ、「景気」が30.3%で、昨年1月の前回調査から11.3ポイント増えた。「良い方向に向かっている」分野では「景気」は同11.6ポイント減の10.4%にとどまり、安倍政権の経済政策「アベノミクス」の恩恵を国民が実感できていないことがうかがえる。
調査は今年1〜2月、全国で20歳以上の1万人を対象に面接方式で実施し、6011人から回答を得た。回収率は60.1%だった。
「悪い方向」は「国の財政」が39%(前回比6.2ポイント増)で最も多く、「物価」が31.3%で続いた。
「良い方向」は「科学技術」が30.1%(同5ポイント増)で最多。次いで「医療・福祉」が26.7%、「防災」が21.3%だった。
国の政策に民意が「反映されていない」との回答は69.4%で、「反映されている」の27.6%を大きく上回った。【松本晃】 -
リアル島耕作! 大企業でゴボウ抜き人事が大流行する理由
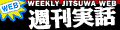
『課長島耕作』の人気キャラクター中沢喜一は、取締役末席から35人のごぼう抜きで社長に指名される。そんな大抜擢人事のサプライズが現実に相次いでいる。
4月1日付で三井物産の社長に就く安永竜夫執行役員(54)は、取締役を経験しないまま上席役員32人を飛び越えての就任。自動車部品大手デンソーの有馬浩二専務役員(57)と富士通の田中達也執行役員常務(58)は、14人抜きで6月の株主総会後に就く予定。6月末に取締役常務執行役員から味の素社長になる西井孝明氏(55)は7人抜きで、こちらは創業家を除いて最年少社長の誕生だ。
各社とも「変革期への対応」「グローバル戦略」など過去のシガラミにとらわれない刷新人事を強調するが、某大手商社役員OBは「後継者を指名する際、現社長には思惑が働く。要するにどうすれば影響力を残せるかに腐心する。院政を敷くかどうかはともかく、だから会長ポストに固執する。もしそんな考えがサラサラないならば、潔く会社と決別しています」と指摘する。
抜擢された社長にとって悩ましいのが、元上司だった面々への対応である。年上でもあり、手のひらを返したように接すれば反発を買う。元上司にしても、社長就任を機にペコペコするのは屈辱でしかない。そこで目障りな上席役員を次々と子会社に“パージ”するケースが多い。前出の商社OBが喝破する。
「これを露骨にやると、人事権を発動した社長だけでなく会長までもが恨まれる。といって粛清組を少なくすれば、社長は彼らの扱いに頭を悩ませる。これまで大抜擢人事が少なかったのは、企業が長年培った人事戦略の賜物だったのだから皮肉なものです」
このトレンドに“便乗”したのがトヨタ自動車で、創業以来初めて外国人の副社長と女性常務役員(こちらも外国人)を誕生させる。豊田章男社長の存在感は揺るがず、世界に向け「開かれたトヨタ」をアピールするなど宣伝効果は抜群だ。
たとえ秘めた魂胆がどうであろうと、こうした人事が世間の耳目を集めることは間違いない。
