国際
-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
20歳の黒人逮捕=警官銃撃事件―米ファーガソン
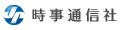
【シカゴ時事】米ミズーリ州ファーガソンで今月12日に警官2人が銃撃され重傷を負った事件で、セントルイス郡警察は15日、第1級暴行などの疑いで、近くに住む黒人の男、ジェフリー・ウィリアムズ容疑者(20)を逮捕した。米メディアによると、同容疑者は発砲の事実は認めているが、「警官ではなく、口論となった相手を狙った」と供述している。警察は供述の裏付けを急いでいる。
調べによると、ウィリアムズ容疑者は11日夜、ファーガソン警察署の周辺で行われた抗議行動に参加。この際に誰かと口論になり、いったん立ち去った後、再び戻ってきて、12日未明に車の中から発砲したと供述している。同容疑者は、盗品譲り受けの疑いで保護観察中だった。
ファーガソンでは昨年8月、丸腰の黒人青年が白人警官に射殺され、大規模な抗議行動が発生。市警察トップのジャクソン本部長の辞職が今月11日に発表されたものの、改革が不十分だとして同日夜から12日未明に再び抗議行動が起き、警戒中の警官2人が銃撃された。
PR -
アサド政権と「交渉必要」 シリア内戦でケリー長官

【ワシントン共同】ケリー米国務長官は米CBSテレビが15日放送した番組で、泥沼化するシリア内戦の収束に向け同国のアサド政権と「最終的には交渉する必要がある」と表明した。米政権はこれまで、アサド政権に正統性はないとして退陣を迫ってきたが、アサド大統領を交渉相手と認めたとも取れる発言。
シリアとイラクで過激派組織「イスラム国」掃討作戦を進めるため、シリア当局との協力を模索している可能性もある。ケリー氏は5日、訪問先のサウジアラビアで「イスラム国壊滅ほど優先度が高いものはない」と語っていた。
-
児童への愛情に満ちている・・日本でよく見る風景に感心、「本当にいいアイデア」「これじゃあそもそも…」―中国ネット

中国版ツイッター・微博(ウェイボー)で46万人以上のフォロワーを持つ中国のネットユーザーが11日、日本の一般的な街頭の風景を撮影した写真を掲載したところ、多くのネットユーザーが注目した。
【その他の写真】
写真からは、信号のある横断歩道へとつながる短い路地に設置された6つの白い障害物に、それぞれ「とびだしだめ」、「とまれ」といった注意が書かれていて、黄色い帽子を被った小学生が車止めを避けながらこの路地を歩いている様子が見える。
ツイート主は画像とともに「日本では、児童による道路への飛び出しを防ぐために安全防護がされている。細かい部分に、児童を愛護する意識が満ちている」と評した。
このツイートに対して、多くのユーザーがコメントを残していった。以下がその一部だ。
「本当にいいアイデアだ」
「広めるべき! 細かい部分においても命を大事にしている」
「強い民族には、そうなる道理がある」
「細かい部分で成否を決する民族を軽視してはいけない」
「人に思いやりのあるデザイン。日本には中国が学ぶべき部分がまだまだある」
「日本の子どもの帽子と学生服がとてもかわいい」
「日本人の細かい部分に対する高い要求には本当に心から賞賛せざるを得ない」
「日本は偉大な国だ」
「日本の民族に敬服せざるを得ないと感じる時が多い」
「日本の駅で見た『教育はもっとも廉価な国防』という言葉に非常にびっくりした。いい事言うよね。共に日本を見習おうじゃないか」
「中国は人が多いから、こんなことしたら道を歩くのにいちいち行列を作らなきゃいけなくなるんじゃないの?」
「どうりで日本のサッカーが強いわけだ。小さいころから障害を通る練習してるんだもん」
「中国だったらとっくに盗まれたよ」
「視覚障がい者にとってはかなり不便」
「これじゃあそもそも防ぎきれない。走るやつは走る」
「あちらの児童は国の屋台骨であり花だ。われわれの児童はいまだにいつでも誘拐されかねない状態。この差は……」
「中国だったら、まさに車がこの路地を通らないように遮るための『車止め』として設置されるんだろうな」
「やたらに崇拝してはいけない! これは明らかに『車止め』であって、自動車が路地に入らないようにするものだ」
(編集翻訳 城山俊樹) -
米ファーガソンの発砲男逮捕 警官狙ってないと供述

【ニューヨーク共同】黒人差別で揺れる米中西部ミズーリ州ファーガソンで、市警前を警戒していた警察官2人が撃たれ負傷した事件を捜査しているセントルイス郡検察は15日、暴行などの容疑で、地元に住む黒人のジェフリー・ウィリアムズ容疑者(20)を逮捕、訴追したと発表した。自宅から拳銃を押収した。
検察によると、容疑者は車内から発砲した。「口論した相手を撃った」と供述し、警官は狙っていないと強調した。しかし事件では、抗議デモの住民側と対峙していた警官2人だけが撃たれており、検察が供述の裏付けを進める。
-
<ウクライナ>住民祈る早期終戦…東部ドネツク

【ウグレゴルスク(ウクライナ東部)真野森作】ウクライナ政府軍と親ロシア派武装勢力がにらみ合うウクライナ東部ドネツク州。2月中旬の停戦直後に親露派が制圧した要衝デバリツェボの近郊ウグレゴルスクに15日、入った。停戦直前まで戦闘が続いた町では大破した建物が目立ち、地下室などで戦火をしのいだ住民がパンの配給に列を作っていた。一帯の支配勢力はウクライナ軍から親露派へ変わったが、「戦争さえなければどちらでもいい」との率直な声も聞かれた。
◇傷痕生々しく
ウグレゴルスクは、デバリツェボから西へ十数キロ離れた小さな炭鉱町。町の入り口に土のうで築かれた「検問所」のコンクリートブロックには、青と黄2色のウクライナ国旗が描かれたままだ。取材には親露派「国防省」の特別な許可が必要で、緊張した空気が感じられた。
「ウクライナ軍の狙撃手がまだいるかもしれない。あまり奥には行くな!」。案内役の戦闘員が声を張り上げた。平時に約8000人だった人口は10分の1近くまで減ったとみられる。子供や女性の多くが避難したためだ。冷たい風の下、ゴーストタウンのように静まり返っていた。
唯一活気があったのはパンの配給所。約50キロ先の町から毎日運ばれ、1日に1人1個ずつ配られる。20人ほどの列にいたボリスさん(74)は「戦争で年金が受け取れなくなり、この先どう生活すればよいのか」と途方に暮れていた。
