社会
-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
警視庁、トラック事故現場近くで安全運転呼びかけ

今月10日、東京・多摩市で自転車で横断歩道を渡っていた小学2年生の女の子が大型トラックにひかれて死亡したことを受け、警視庁は現場近くで安全運転を呼びかけました。
「交差点を曲がる際とか、歩行者の横断に気をつけて」(警察官)
都内では、今年に入り交通事故で37人が死亡していて、半数近くがトラックに絡む事故だということで、警視庁が注意を呼びかけています。(17日18:07)PR -
懐柔策か 取材機会か 首相とメディアの会食にはどんな問題があるのか?

会食の回数、突出
読売新聞の渡辺恒雄グループ本社会長、産経新聞の清原武彦会長、フジテレビの日枝久会長……。2012年末に第2次安倍政権が誕生して以降、大マスコミのそうそうたるメンバーが首相と会食しています。「首相動静」によると、読売新聞や産経新聞といった保守色の強いメディアばかりではありません。毎日新聞、朝日新聞、テレビ朝日、日本テレビ、共同通信など全国メディアのトップはこの間、ほとんどが首相と会食を持ちました。中日新聞(名古屋)、中国新聞(広島)、西日本新聞(福岡)などの有力地方紙社長とも会っています。
昨年12月の東京新聞によると、安倍首相とメディアの夜会食は、就任後の2年間で40件以上になったそうです。2008年から1年間首相だった麻生太郎氏(現財務相)は10件以下。2009年から3年間の民主党政権時代は、3人の首相合わせて11件しか確認できなかった、としています。
安倍首相は経営陣だけでなく、各社の政治部長や首相官邸キャップらとも頻繁に会食しています。有力紙の記者は「小泉政権時代も首相・メディア幹部の会食はあったが、これほど多くなかった。国政選挙や重要政策の決定直後に会食が多いのも特徴」と言います。
実際、昨年12月には衆院選から2日後の夜、東京の高級寿司店で各社の編集委員・解説委員クラスとの会食があり、出席者の1人だった記者が、集まった番記者らに「内容はオフレコだ」と“解説”してみせる一幕もありました。
メディア懐柔策?
こうした会食は、どこに問題があるのでしょうか。まずは「なぜ会食するのか」の言い分を見てみましょう。
朝日新聞は1月14日の「お答えします」欄でこの問題に言及。安倍首相と親しいことで知られる曽我豪編集委員が「最高権力者である総理大臣がどういう思いで政治をしているのかを確かめる取材機会を大事にしたい」とコメントしました。高級店での費用は首相分も含めて参加者の割り勘、だそう。同様の説明は他のメディアからも出ています。
会食場所は名店や高級店、ホテル内のレストランがほとんどで、料金は1人1万円~3万円のようです。決して安くはありませんが、店選びには警備当局の判断も働くので、「安い・高い」を軸に考えるのはここでは控えておきます。では、会食問題はどう考えればいいのか、報道現場の声を拾ってみました。
あるテレビ局のデスクは「まずは回数の問題」と言います。
「首相とテーブルを囲む時間が増えると、どうしても相手と一体化していく。会食しながら厳しく問いただしていけるか。しかも内容はオフレコ。厳しく接していると反論しても誰も信じない。視聴者にどう見えているかも考えず、権力者との近さを社内や業界内で誇っているだけ」
メディアの経営陣が首相と会食する、そのこと自体を問題視する声も強くあります。次は官邸詰めの記者。
「日本のマスコミは報道だけでなく、不動産や広告、イベントなど多様な事業部門を抱えているのに、主力の広告収入は減り、どこも先行きが見えない。そんな中、例えば、一大イベントの2020の東京五輪に向けて政府と協力してください、と首相に言われたら、経営陣はいろんな計算を働かせるでしょう」
次ページは:「どう見えているか」が見えていない大手メディア 前へ12次へ2ページ中1ページ目を表示
-
「八紘一宇」礼賛はヤバいのか 侵略と家族と三原発言の関係

自民党の三原じゅん子参院議員が、国会質疑で「八紘一宇」というスローガンを「日本が建国以来大切にしてきた価値観」として紹介し、波紋が広がっている。この言葉は、元々は「世界を一つの家とすること」という意味で登場する。だが、それが派生する形で「侵略を正当化するために使われたスローガン」だと受け止められることも多い。
早くも韓国では、「侵略戦争のスローガンを礼賛」などと批判が出ている。
■元々の意味は「全世界を一つの家にする」
三原氏は2015年3月16日の参院予算委員会で、アマゾンをはじめとする多国籍企業の課税回避の問題について質問する中で、
「そもそも、この租税回避問題というのは、その背景にあるグローバル資本主義の光と影の、影の部分に、もう私たちは目を背け続けることはできないのではないか」
と問題提起。その後、「八紘一宇」という単語を持ち出した。
「そこで、今日、皆様方にご紹介したいのが、日本が建国以来大切にしてきた価値観『八紘一宇』」
「八紘一宇」とは、日本書紀の文言をもとに戦前の宗教家、田中智学が1913年に使い出した言葉だ。「八紘=8つの方角=全世界」「宇=家」を意味し、「全世界を一つの家にする」という意味だが、三原氏は「昭和13(1938)年に書かれた『建国』という書物」から引用しながら、こう説明した。
「八紘一宇とは、世界が一家族のように睦(むつ)み合うこと。一宇、すなわち一家の秩序は一番強い家長が弱い家族を搾取するのではない。一番強い者が弱い者のために働いてやる制度が家である。これは国際秩序の根本原理をお示しになったものであろう。現在までの国際秩序は弱肉強食である。強い国が弱い国を搾取する。力によって無理を通す。強い国はびこって弱い民族を虐げている。世界中で一番強い国が、弱い国、弱い民族のために働いてやる制度が出来た時、初めて世界は平和になる」
次ページは:「麻生大臣!この考えに対して、いかがお考えになるか」 前へ12次へ2ページ中1ページ目を表示
-
元東大教授が無罪主張=研究費詐取事件―東京地裁
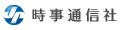
架空の業務を発注し、東京大などから研究費約2100万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた同大政策ビジョン研究センターの元教授秋山昌範被告(57)の初公判が17日、東京地裁(稗田雅洋裁判長)であった。秋山被告は「私は無罪です」と起訴内容を否認した。
検察側は冒頭陳述で、秋山被告が実質経営する会社の運転資金に充てるため、自身が関与する研究事業について、業務受注の事実はないのに関係会社に虚偽の請求書などを作成させ、研究費を大学側から詐取したと指摘した。
弁護側も冒頭陳述を行い、被告が実質経営する会社と関係会社が協力して事業を実施し、成果として医療情報システムが完成したと主張。高い評価を得ており、業務に実体はあったと訴えた。
-
機動隊員が語るオウム強制捜査で活躍の「カナリア」

カナリアは鳴き声が美しい鳥としても知られています。空気の変化に敏感で、有毒ガスが発生するとすぐに死んでしまいます。昔は炭鉱で働く人がガスを察知するために連れて歩いたそうです。つまり、命と引き換えに人間に危機を知らせてくれた鳥です。実は20年前のオウム真理教をめぐる事件の捜査でも、捜索隊の先頭を切っていたのは、カナリアでした。
地下鉄サリン事件が起きた2日後の1995年3月22日。警視庁は、山梨県上九一色村のオウム真理教の拠点を一斉捜索しました。ガスマスクをつけた機動隊員が手にしていたのは「カナリア」。
「サリン製造工場」第7サティアンの捜索にもカナリアが参加。このときカナリアを持っていた機動隊員が、初めてカメラの前で語りました。
「私は手にカナリアを持って入っていたので、一番先頭で入っていったと記憶している」(警視庁第三機動隊・遠塚章弘警部補)
なぜ、カナリアだったのでしょうか
「毒物に敏感なので、一緒に入ればすぐに反応してくれる 」(警視庁第三機動隊・遠塚章弘警部補)
カナリアやメジロは汚染された空気に敏感で、炭鉱などでガス漏れを調べるのに使われた歴史があります。地下鉄にまかれたサリンは異臭がしましたが、本来、サリンは「無臭」。毒ガスを”検知”するため自衛隊のアドバイスを聞き、カナリアが選ばれたのです。
捜索直前、「学校で飼育するため」と目的を隠して都内のペットショップなどからおよそ20羽が買い集められました。そして、迎えた捜索当日。
「『しっかり頼むよ』と『お前任せたからね』と」(警視庁第三機動隊・遠塚章弘警部補)
カナリアは、2日間活動したあと2日間休むペースで捜索の先頭に立ち続けました。
「本当に終始おとなしい状態で」(警視庁第三機動隊・遠塚章弘警部補)
その後、カナリアはどうなったのでしょうか。東京・目黒区にある第三機動隊。捜索が行われた年の7月、つがいのカナリアから1羽のひなが生まれました。その名前は・・・。
「『ピース』という名前をつけた。平和の意味をこめてつけた」(警視庁第三機動隊・遠塚章弘警部補)
平和を願ってつけられた「ピース」という名前。隊員の心の支えになったと言います。カナリアは、それぞれの機動隊に大切に育てられました。
今月、警視庁が行ったサリンによるテロを想定した訓練。隊員の手にはカナリアではなく、最新式の「ガス検知器」が握られていました。…
