社会
-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
沖縄知事、辺野古移設で岩礁破砕許可取り消しへ

沖縄県の翁長雄志(おなが・たけし)知事が米軍普天間飛行場(同県宜野湾(ぎのわん)市)の名護市辺野古移設で岩礁破砕許可の取り消しに向け、週内にも最終調整に入ることが22日、分かった。許可取り消しで海底ボーリング調査など防衛省の海上作業を阻止する狙いがある。防衛省はボーリング調査には岩礁破砕許可は不要との主張を崩さず、許可が取り消されても調査を続行する方針だが、埋め立てを行えなくなる恐れがある。
防衛省は12日に辺野古沖でボーリング調査を再開するにあたり、ブイ(浮標)とフロート(浮具)を固定するコンクリート製ブロックを臨時制限区域内に投下した。
県は岩礁破砕を許可した埋め立て予定区域の外でブロックが投下され、サンゴ礁が傷つけられたとして、協議や岩礁破砕許可の取り直しなどの手続きを行うよう指示したが、防衛省が拒否しているため、許可取り消しを検討している。
PR -
動植物41種を希少種指定へ クメトカゲモドキなど

環境省は23日、ヤモリの仲間で絶滅危惧種のクメトカゲモドキなど動植物41種を、捕獲や譲渡が禁じられる国内希少野生動植物種(希少種)に指定する方針を明らかにした。絶滅危惧種を保全するため、2020年までに300種を追加指定する予定。
新たな指定対象は、政府が世界自然遺産登録を目指している「奄美・琉球」(鹿児島、沖縄)に分布するトカゲモドキ属5種と植物6種。小笠原諸島に分布する固有種の昆虫類16種、陸産貝類14種も含む。23日の中央環境審議会で示された。
環境省によるとトカゲモドキは、マングースによる捕食やペットにするための違法採取が問題になっていた。
-
東京でソメイヨシノ開花

きょう23日、関東のトップを切って、東京都心でソメイヨシノが開花しました。平年より3日早く、昨年より2日早い「サクラサク」便りです。
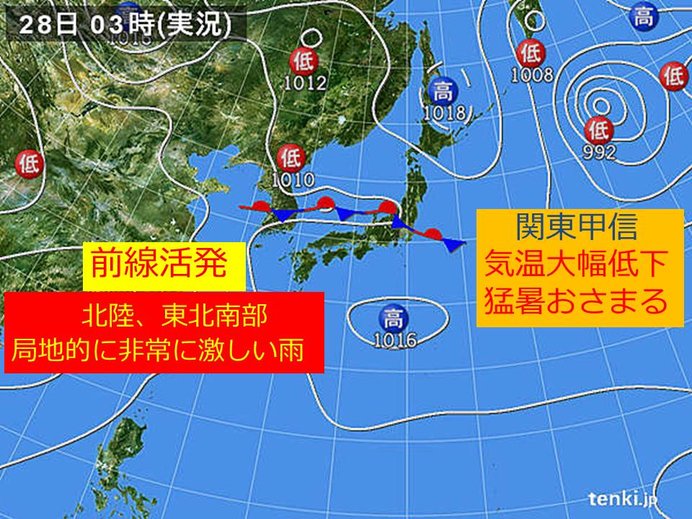
3月20日発表の開花予想
23日、東京管区気象台は「桜(ソメイヨシノ)の開花」を発表しました。
平年より3日早く、昨年より2日早い。
関東ではトップの開花です。
※「サクラの開花日」とは、標本木で5~6輪の花が咲いた状態となった最初の日をいいます。
なお、本日、
岐阜でもソメイヨシノの開花が観測されています。
(平年より3日早く、昨年より1日早い)
上の図は、先日、20日発表の桜の開花予想。
桜前線は、4月の上旬には北陸、東北南部へと進んでいくでしょう。
なお、昨日までに開花した地点については、
下のリンク、『サクラ開花の便り続々と(木村予報士の記事)』をご覧ください。桜は、一般的に咲き始めてから1週間程度で、満開を迎えます。
東京では3月31日に満開になる予想です。
(3月20日の時点での予想)
開花から10日間くらいは、強い風や雨でも散ることはなく、
美しい花を楽しむことができるでしょう。
tenki.jpで、天気をチェックして、お花見を楽しんで下さい。 -
沖縄県、作業許可取り消し検討 辺野古ブロック撤去指示へ

沖縄県は23日、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設先、名護市辺野古沿岸部で沖縄防衛局が海底ボーリング調査のため投入したコンクリート製ブロックがサンゴ礁を損傷したとして、県漁業調整規則に基づき、ブロック引き上げなど原状回復と海上作業の一時停止を月内に指示する方向で調整に入った。指示に従わなければ、海底の岩石採掘と土砂採取など岩礁破砕に関する許可の取り消しも検討する。
県関係者が明らかにした。
ブロックは米軍や工事専用船舶以外の航行を禁じる臨時制限区域を明示するためのブイやフロート(浮具)の重り。引き上げれば、ボーリング調査に影響が出る可能性もある。
-
婚活支援・防犯カメラ…地方創生、知恵比べ

地方創生に向けた国の交付金(総額4200億円)の使い道について、各自治体が知恵を絞っている。
婚活支援、防犯カメラ、商品券……。ユニークな事業が並ぶが、どんな事業が「地方創生」につながるのかは必ずしも明確でなく、単なるばらまきに終わらせないための工夫が求められそうだ。
◆一気呵成
1970年の大阪万博に合わせ街づくりが進んだ大阪・千里ニュータウン。街路樹の老木化が進んでいるため、吹田市は交付金6000万円を充てて倒木の危険性などを調べる。元々、新年度予算に計上予定だったといい、「基金の取り崩しを減らせた」と担当者。
交付金支給が決まったのは昨年末だ。自治体側は2014年度補正予算案に事業を盛り込まなければならず、急ピッチでの検討を強いられた。地元産品を海外に売り込む事業などを展開する愛媛県の担当者は「内容を決めるまで3週間ぐらいしかなかった。一気呵成(かせい)に予算化した」と語る。
◆創意工夫
各自治体の「知恵比べ」となったのが「地方創生先行型」交付金。今後3年間で防犯カメラ1000台を設置する兵庫県伊丹市は、費用の一部に交付金を充当する予定で、藤原保幸市長は「治安を良くし、『選ばれる街』にしたい」と狙いを語る。
婚活支援に乗り出すのは京都府。4年間で1000組の成婚を目標に、相談窓口を設置したり、セミナーを開いたりする。愛媛県八幡浜市は、閉校になった学校の校舎を利用し、ミカンの収穫を手伝うアルバイトの宿泊施設を整備する。
観光振興に力を入れる自治体も。京都府宇治市は、鵜(う)を綱でつながず、自由に泳がせて魚を取らせる伝統漁法「放ち鵜飼い」の復活に取り組む。
◆経済効果
「地域消費喚起・生活支援型」の交付金では、「プレミアム付き商品券」を発行する自治体が多い。大阪市は夏頃、市内の登録店で使える商品券(1万2000円分)を1万円で販売。神戸、京都、堺各市などもプレミアム(上乗せ)率を20%とする予定だ。
交付金については「統一地方選を意識した政府のばらまき」(ある自治体の担当者)との声も出ているが、児童福祉施設に入る子どもたちへの1万円分の図書引換券配布などを行う兵庫県の井戸敏三知事は「消費はばらまかないと増えない」と肯定的だ。
みずほ総合研究所の風間春香・主任エコノミストは「自治体の工夫次第では、予想以上の経済効果が表れる可能性はある。ばらまきに終わらせないためには、国が取り組みを整理、検証するべきだ」と指摘している。
◆地方創生に向けた国の交付金=景気の下支えなどを目的とした「地域消費喚起・生活支援型」(2500億円)と、地域の実情に応じた取り組みを支援する「地方創生先行型」(1700億円)の2種類。人口規模などに応じ、すべての都道府県、市区町村に配分される。政府が昨年末に閣議決定した緊急経済対策に盛り込まれた。
