国際
-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
尖閣地図公開で反論=中国
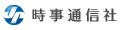
【北京時事】中国外務省の洪磊・副報道局長は17日の記者会見で、日本外務省が沖縄県・尖閣諸島(中国名・釣魚島)を「尖閣群島」などと日本側の呼称で表記した中国政府発行の地図を公開したことに対し、「釣魚島が中国に属するのは否定できない事実だ。1、2枚の地図を探し出したところで覆せるものではない」と反論した。
洪副局長は中国側の領有権主張が「十分な歴史と法理に基づいている」と強調。「必要ならば、釣魚島が中国に属していることを示す地図を100枚でも1000枚でも探し出せる」と強弁した。
PR -
フセイン元大統領の墓破壊=「イスラム国」との交戦下―イラク北部
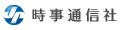
【カイロ時事】イラクからの報道によると、イラク軍部隊が過激派組織「イスラム国」から奪還した北部ティクリート近郊アウジャにあったフセイン元大統領の墓がほぼ完全に破壊されていたことが17日明らかになった。誰が破壊したのかは不明。
同組織は、イラク北部で歴史的な文化財の破壊を繰り返している。一方、軍部隊に加わるイスラム教シーア派の兵士や民兵の間では、過去の弾圧から元大統領への憎しみや反感が強く、制圧した現場で墓の破壊を喜ぶ映像がインターネット上に投稿された。
-
人質事件のカフェ、再開へ=追悼プレート設置―豪シドニー
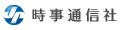
【シドニー時事】昨年12月に人質立てこもり事件の舞台となったオーストラリア・シドニー中心部のカフェ「リンツ」が、今月20日に再開されることが決まった。運営会社が17日発表した。
事件では、過激派組織「イスラム国」に傾倒した男が人質を取ってカフェに立てこもり、男女2人が犠牲になった。銃撃戦で店内が著しく損傷したこともあり、店舗は閉鎖されるとの見方があった。
運営会社は「議論の結果、店を再開し、前に歩み出すことが最善と判断した」と説明。店内に、亡くなった2人を追悼するプレートを設置するという。
-
米教科書の訂正求める=慰安婦記述で日本歴史家
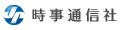
旧日本軍の従軍慰安婦問題をめぐり、日本政府が米国の高校教科書の記述訂正を求めた問題で、日本の歴史家19人が17日、この教科書に「不適切な箇所がある」として、出版元の米マグロウヒル社に8カ所の訂正を求めた。
東京都内で記者会見した現代史家の秦郁彦氏は「日本軍は20万人もの女性を強制的に徴用した」との説明について「強制連行する必要はなかった」「誇大な数字だ」と指摘。また、慰安婦を「天皇からの贈り物」と記述している点について「あまりにも非常識な表現」と述べた。
日本政府は昨年12月、「重大な事実誤認がある」と同社に訂正を申し入れた。これに対し、米国の歴史学者20人が今月2日、連名の声明を発表し、「国家や利益団体が出版社や歴史家に圧力をかけることに反対する」と批判していた。
-
中国主導のアジアインフラ投資銀行に独・伊・仏も参加へ=豪州、韓国、カナダも検討、日本は孤立か―国際金融筋

2015年3月17日、国際金融筋によると、中国主導で今年末にスタートするアジアインフラ投資銀行(AIIB)に、英国に続いてドイツ、フランス、イタリアが参加する見通しになった。主要7カ国(G7)の大半が参加することになり、国際金融機関として信認が高まる。カナダやオーストラリア、韓国なども追随する可能性があり、慎重姿勢の日本の判断が注目される。
【その他の写真】
経済成長が著しいアジアでは、成長を支えるために、毎年少なくとも7500億ドル(約95兆円)に上るインフラ投資が必要とされている。このニーズを狙って、中国が「新興国による新興国のための国際投資機関」を標榜して主導したのがAIIB。上海に本部を置き資本金は1000億ドル(約12兆円)。出資比率はGDP(国内総生産)に基づいて決まるため、参加国中最大の経済大国、中国が半分以上の出資比率を確保、大きな発言権を握ることになる。
この投資銀行には、東南アジア10カ国、インド、ニュージーランドなど28カ国の参加が既に決まっており、30カ国を超えることになる。南シナ海で中国と対立するフィリピン、ベトナムも加わっている。アジア専門家によると、深刻な投資資金不足にあえぐアジア諸国にとって、立ち遅れたインフラ整備を支援するという、中国の提案を拒否する理由は見当たらないという。先進国のインフラ開発会社や商社などは「参加しないと21世紀の有望市場・アジアの事業などで不利になるのでは」と懸念している。
AIIBと役割が似た国際機関としては、世界銀行やアジア開発銀行(ADB)がある。それぞれ米国と日本の発言力が強く、歴代総裁ポストは世銀が米国人、ADBは日本人が就任する。中国をはじめとする新興国が発言権の増大(出資分担金増)を求めるIMF改革は米議会が承認せず実現していない。現状に不満を抱くブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの新興5カ国(BRICS)は14年7月、「BRICS開発銀行」の設立でも合意に至った。
一方、中国はAIIBへの参加を日本、米国にも要請。「日本はアジアの重要な国であり、日本もアジアの発展に向けてAIIBで重要な役割を担ってほしい」と伝えてきたという。AIIBは中国の巨額資金が拠りどころ。中国の国益を優先する「世界戦略の先兵となるのでは」との懸念は拭えない。しかし、G7の大半が参加することで、発行債券などの格付けが上がり、低金利での資金調達が可能となる。
中国は6月末までに各国の出資比率などをまとめた設立協定を結ぶため、3月末までに創設当初の参加国を確定する方針だ。米国も参加国増加は止められないと見てAIIBを容認する姿勢に転じている。日本は難しい判断を迫られるが、「孤立を防ぐため関与し、内側から日本の立場を反映すべきだ」との意見もある。(八牧浩行)
