社会
-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
<オーロラ>北海道の一部で淡く薄いピンクの光確認

17日夜から18日未明にかけ、北海道の一部で淡いピンク色のオーロラが観測された。日本で確認されたのは2004年11月以来という。観測したなよろ市立天文台(名寄市)の佐野康男台長は「前回より淡く、肉眼でほとんど見えないレベルだった」と話した。
オーロラは、太陽からの粒子によって地球の大気が光る現象で、通常は極域に現れる。上出洋介・名古屋大名誉教授によると、今回は活発な太陽活動で地磁気が2度にわたって乱れ、粒子の振り込む場所が変わり、世界各地の比較的緯度の低い地方でもオーロラが現れたという。【西川拓】PR -
<公示地価>震災爪痕残る千葉・我孫子は最大の下落率11%

災害を背景とする地価の変動が、各地で続いている。18日に公表された公示地価では、東日本大震災による液状化や台風で被害を受けた千葉県我孫子市の地価が大きく下落した。一方で、内陸部に位置し、津波の危険が小さいとみられている静岡県藤枝市の地価は上昇。被災リスクの差が明暗を分けた格好だ。
住宅地で全国最大の下落率(10.9%)となった我孫子市布佐酉町。理容業を営む川添勝順さん(70)が嘆いた。「景気の良い頃はよく稼いだけど、今はほとんど客がない。震災や水害の後、新しく移り住む人は少ない」
同町を含む布佐地区は、東日本大震災による液状化の被害が集中し、約120戸が「全壊扱い」となった。追い打ちをかけたのが2013年10月の台風26号の水害だ。総雨量282ミリという記録的な豪雨が震災時の広範囲な地盤沈下と重なり、約400戸が浸水するなど大きな被害が出た。家が取り壊された空き地が点在し、地区の外に転居したまま戻らない人も少なくない。
水害対策として、従来の7.6倍の処理能力をもつポンプ場が今月末に稼働する。しかし地盤強化のための再液状化防止策は費用負担を懸念する住民が反対し、実現しなかった。
地元の不動産業者は「以前は土地も安くすれば売れたが、今は買い手が見つからない」と言う。市課税課は「長い目で見れば、固定資産税が減り、市財政に影響を及ぼすだろう」との見通しを語る。
藤枝市は、静岡市に20分以内で通勤できる内陸のベッドタウン。以前から人口は増えていたが、津波リスクを避けようとする人が沿岸部などから転入し、地価が0.2%上昇した。
JR藤枝駅の周辺は高層マンションが建ち並び、さらに建設工事が続く。東日本大震災の起きた11年から今年2月までに、同市の住民は1500人以上増え、約14万6500人になった。
市内の不動産業者は「沿岸部からの流入が一段落したら土地の需要は細るのでは」と慎重だ。だが市は、駅周辺の図書館や公園の整備で子育て世代の転入促進を図る。市の担当者は「便利になった市街地が新住民を引きつけ、活性化につながっている」と話す。【橋本利昭、平塚雄太】 -
<安保法制>道筋急ぐ自民 地方選意識の公明党…思惑が合致

自民、公明両党は18日、安全保障法制の骨格について実質合意した。4月末に予定される日米防衛協力の指針(ガイドライン)の見直しを前に、国内法整備に道筋をつけたい政府・自民党と、今月26日から始まる統一地方選への影響をできるだけ小さくしたい公明党の思惑が合致した。
18日の与党協議会後、自民党の高村正彦副総裁と公明党の北側一雄副代表はそろって記者団の取材に応じた。高村氏は「相場観としてはこういうことだろうという共通認識はあると感じた」と表明。北側氏は「まだ大事な課題が残っている」と述べたものの、具体的な対立点についての言及は避けた。
両党が20日、合意文書案を正式に了承するのを受け、政府は法案の作成作業に入る。与党は4月12日の統一地方選前半戦(知事選など)が終わった後、協議を再開する方針だ。
合意文書案は、武力紛争に対処している他国軍を後方支援する恒久法について、「国会の事前承認を基本とする」とのみ記載。公明党は、国際協力は日本有事などに比べ緊急性が低いため「例外なく事前承認」と国会が歯止めをかけることを要求していた。
また、国連主導ではない平和協力活動に道を開く国連平和維持活動(PKO)協力法改正についても、同党は派遣に際して「国際法上の正当性」を明確にするよう求めていたが、合意文書案では、派遣は「国連決議等がある」場合とあいまいにした。
同党にとって統一地方選は、国政選挙以上に重要な選挙だ。与党協議が長引けば、選挙準備に影響するだけでなく、与党内の溝を野党の批判材料にされかねない。協議を長引かせても「プラスなことは何もない」(公明党幹部)というのが本音だった。
一方、政府・自民党としては、4月末までに日米でガイドライン見直しに合意するためには、公明党と現状で可能な範囲で折り合い、安保法制の整備が既定路線だと米側に示す必要があった。合意文書が整わないまま日米のガイドライン協議が始まれば、「対米追随」との批判を浴びるという懸念も出ていた。【高本耕太、飼手勇介】 -
事業再開すれば「裁量逸脱」=林道支出差し止めは認めず―那覇地裁
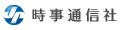
国の天然記念物ヤンバルクイナなど野生動植物の宝庫として知られる沖縄本島北部の山地「山原(やんばる)」の林道開設事業をめぐり、県民9人が県知事に公金支出の差し止めなどを求めた訴訟の判決が18日、那覇地裁であった。鈴木博裁判長は「事業は休止中で、公金支出の確実性が予測されない」などとして訴えを退けたが、「現状のまま事業を再開すれば、裁量権の逸脱・乱用と評価されかねない」と述べた。
裁判の対象となったのは、県の森林計画に盛り込まれた国頭村内の林道30本に対する支出。事業として採択されたのは11本で、このうち5本は完成している。
判決は休止中の6本について、「調査、検討をした上で実施の可否を判断するため、支出が確実とは言えない」と判断。一方、休止から既に7年以上経過した現在も、県が必要な調査を行っていないと述べ、このまま事業を再開すれば違法となる可能性を指摘した。
翁長雄志知事は今後の事業について、「世界自然遺産登録に向けた取り組み状況を勘案し、地元や関係機関と調整しながら判断したい」とのコメントを発表した。
-
<誤飲>洗濯用パック型液体洗剤の事故 発売1年で152件

消費者庁と国民生活センターは18日、洗濯用パック型液体洗剤の誤飲などの事故が3歳以下の乳幼児を中心に相次いでいるとして、子供の手の届かない場所に保管するよう注意を呼びかけた。
この洗剤は濃縮液体洗剤を水溶性のフィルムで包んだもの。昨年4月の発売以来、消費者庁には152件の事故情報が寄せられ、うち入院した事例が8件あった。0〜3歳の事例が110件で約7割を占め、「子供が握ったら破裂し目の中に入った」(3歳女児)、「子供が箱から取り出して遊んでいたところ飲み込んだ」(1歳男児)などの例があった。
万が一飲んでしまった場合は、無理に吐かせず、口をすすがせ、水か牛乳を少し飲ませて病院を受診する▽目に入ったら、すぐに水で10分以上洗眼して受診する−−などとアドバイスする。
