社会
-
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
-
ネット使用の人権侵害が最多更新 1400件、法務省集計

法務省は13日、全国の法務局が2014年に救済手続きを始めた人権侵害事案のうち、インターネットを使ったものが前年比49・3%増の1429件だったと発表した。3年連続の増加で、現行と同じ方法の統計が残る01年以降最多となった。
法務省人権擁護局によると、最も多かったのは「プライバシー侵害」の739件。「名誉毀損」の345件が続き、この二つで全体の75・9%を占めた。法務局がネット掲示板の管理者やプロバイダーに削除要請したという。
ネット以外も含めた14年の人権侵害事案の総数は2万1718件で、前年より3・2%減少した。
PR -
対処必要な子供400人=連絡取れず、不良グループと交際―川崎事件で調査・文科省
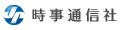
文部科学省は13日、川崎市の男子中学生殺害事件を受けて行った子供の安全に関する緊急確認調査の結果を公表した。不登校で連絡が取れない状態が続いたり、不良グループなどと交際したりする中で、危険な目に遭う恐れのある子供は全国で400人に上り、文科省は「早急に安全を確保する必要がある」として、警察や児童相談所との連携体制をつくって対応するよう各学校に通知した。
-
小泉純一郎 再び始動、再稼働元年に立ちはだかる〈週刊朝日〉

細川護煕元首相と代表理事を務める一般社団法人「自然エネルギー推進会議」の発起人に名を連ねた小泉純一郎元首相が再始動する。原発再稼働元年とされる今年、地方から“乱”を起こすという。
3月11日──。
小泉氏は被災地・福島から本格始動した。同日、地域電力会社・会津電力(福島県喜多方市)の招きに応じ、喜多方市内で「日本の歩むべき道」と題した“脱原発”講演会を行い、怪気炎を上げた。
福島第一原発の汚染水問題を安倍晋三首相らが「アンダーコントロール」と発言していることについて、「全然(コントロール)されてない。よくもああいうことが言えるなと思う」などと厳しく批判した。
さらに関係者によると、初夏にはJパワー(電源開発)が建設中の大間原発(青森県大間町)を視察した後、一部が大間原発の30キロ圏内にある函館市を訪問するプランも持ち上がっているという。工藤寿樹函館市長は昨年、国とJパワーを相手取り、大間原発の建設中止を求めて東京地裁に提訴している人物だ。
「漁船を出して船から大間原発を視察した後、国やJパワーと勇敢に闘っている函館市長を激励に行くという計画です。小泉氏は『脱原発活動は3カ月に1回ぐらいでいい。印象的なタイミングを見計らってやるのがいい』という独自のスタンスを持っているので、3・11から約3カ月後の6月中旬から7月初めぐらいになるのではないか。次男の進次郎氏を自分が行きつけのイタリアンレストランに呼び、よく食事しているので、水面下で連携もあり得るかもしれない」(小泉氏周辺)
大間原発視察の3カ月後の秋には、東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)の再稼働に反対している泉田裕彦・新潟県知事を激励する計画も持ち上がっているという。
泉田県知事は1月6日、柏崎刈羽原発6、7号機の再稼働を前提とした原子力規制委員会の審査状況を報告しに来た東電の広瀬直己社長に対し、「福島第一原発事故の原因究明、検証をしっかりやるのが先だ」と牽制。再稼働の議論に応じない姿勢を強調した。
「いま、国会でわが世の春を謳歌する安倍政権と闘う姿勢を示しているのは、函館市長と新潟県知事ぐらい。彼らをうまくバックアップできれば、地方の乱がさらに広がる可能性がある。昨年来、滋賀、沖縄、佐賀の県知事選で自民党が擁立した候補者は次々と敗北。背景にはトップダウンで国策をゴリ押ししてくる安倍政権に対し、地方の反発がある。小泉さんは安倍政権の弱点は地方とにらみ、『脱原発の包囲網』をジワジワと広げようとしている」(前出の関係者)
(本誌取材班)
※週刊朝日 2015年3月20日号より抜粋 -
東大合格者 開成躍進、公立ダウンの理由は「難問」〈週刊朝日〉

今年の国公立大入試は難しかった。センター試験では新課程となった数学と理科をはじめ平均点が大きくダウンした科目が多く、東大では数学が難問だったといわれる。その結果、東大合格者の高校ランキングでは、開成が躍進して断トツとなり、公立高校が軒並みダウンした。
東大合格者数トップは34年連続となる開成(東京)。前期合格者は2012年の193人から、昨年149人へと大幅に減らしたが、今年は27人増の176人。2位で104人の筑波大附駒場(東京)を大きく引き離した。開成の高三学年主任、五十嵐裕教諭は言う。
「本校では文系も数IIIまで学び、数学が得意な生徒がほとんど。今年の東大の数学は難しかったため、そのことも合格者が増えた一因かもしれません」
やはり前年から19人増の32人と躍進した渋谷教育学園渋谷(東京)。高三学年主任、河口竜行教諭が話す。
「以前は、中3から英語と数学は習熟度別授業を行っていましたが、現高3生からはあまり学力の差がなく、習熟度別授業をしませんでした。みんな仲がよくて、勉強を教え合い、とても雰囲気がよかった。『この大学に入ってこんな勉強をし、将来はこういう職業につきたい』という目標を持ち、切磋琢磨(せっさたくま)していました」
一方で、公立は合格者を減らした学校が目立つ。今年の東大入試は公立に厳しい壁が二つあったようだ。
一つ目はセンター試験が難しかったこと。駿台予備学校進学情報センターの石原賢一さんが解説する。
「センター試験は、数学II・Bと理科が難しかった。特に理系が受けた理科(2)は、初めて全範囲から出題される2科目の受験で負担が重かったうえ、化学と生物の選択問題はいずれも教科書の最後で学ぶ分野から出題されました。高2までに全範囲を終えるのが一般的な中高一貫校に有利で、公立高校では演習問題をやりこむ時間がなかった」
二つ目は東大の2次試験の数学が難問だったこと。
「特に第6問は、最難関の理IIIの受験者以外は解かないほうがいいと思われるほどの難問。数学が得意な生徒が多い、中高一貫校に有利でした」
今年の東大の前期日程の志願者は、昨年より29人増の9444人で、倍率は昨年並みの3.1倍だった。科類別では、文I、文II、理Iが増加した一方、文III、理II、理IIIが減少。特に文IIIでは第1段階選抜(門前払い)が行われなかった。
この志願状況について、石原さんはこう話す。
「15年入試は、国公立大も私立大も『理高文低』が沈静化し、医学部と薬学部の志願者が減った。東大もその傾向があてはまった。文IIIが減ったのは第1段階選抜の予想ラインが高く、敬遠されたからでしょう」
(庄村敦子)
※週刊朝日 2015年3月20日号より抜粋 -
東日本大震災から4年 再エネ抑制策に海外からも異論〈週刊朝日〉

着々と原発回帰を進めている安倍政権。一方、原発回帰とワンセットで進みつつあるのが、太陽光や水力、地熱などの再生可能エネルギーへの締め付けである。
経産省が新たに見直した、再エネの固定価格買い取り制度(FIT)の新ルールでは、これまで電力会社が再エネの発電事業者に出力抑制を無償で求められる限度としていた「年間30日」が「無制限」に変わった。
この決定を受け、九電ら5電力会社は3月4日、出力抑制が最大で年間165日、抑制率は3〜5割になるとの試算を公表した。再エネ発電事業者の経営が不安定になりかねず、再エネ普及のペースが下がることが危惧されている。
出力抑制の根拠として電力業界や経産省が持ち出しているのが、電力の需給バランスの問題だ。火力や原子力と違って発電量が変動する再エネの導入が進み、電力の供給量が需要量を上回ると、電流の周波数が上昇し、電気機器の故障や停電の恐れがあるというのだ。ただ、海外の専門家は日本でのこうした議論に首をかしげている。3月5日、都内で開かれたメディア関係者との懇談会で、系統連系を専門として各国政府等にアドバイスをしている独エナジーノーティックス社のトム・ブラウン上級研究員はこう語った。
「変動する自然エネルギーの普及率が約20%まで進んだアイルランドで周波数の問題が最近指摘され始めたものの、設備の改良などで技術的に十分解決可能で、大きな問題になりませんでした。そもそも日本のような低い普及率(2.2%)で、そのような問題が起こるとは思えない。既存の広域連系線をもっと活用すれば、供給が需要を上回るということも回避できます」
同会で自然エネルギー財団のトーマス・コーベリエル理事長も指摘した。
「ドイツなどでは再エネの優先給電のルールが確立していて、再エネの供給量が増えた時には、火力や原子力の出力を抑制して需給を調整している。日本では電力大手の利益を維持するために火力の出力抑制が不十分で、なにより原子力を優先している。わざわざ海外から高い値段で輸入した化石燃料を燃やして、得をするのは電力大手だけ。国民や政府は、なぜこんなことを許しているのでしょうか」
原子力ムラを慮(おもんばか)り、安倍政権が電源構成の長期目標を示す「エネルギーのベストミックス」をなかなか示さないことにも、再エネ業界はいら立ちをつのらせている。再エネ関連メーカー幹部はこう不満を漏らした。
「原発再稼働するのなら、ベストミックスの電源構成計画をキチンと示すのが筋でしょう。だが、経産省は怖がって官邸に言いだせないようだ。宙ぶらりんの状態で締め付けが続けば、再エネメーカーは市場の試算ができず、金融機関から融資も受けられなくなる」
(本誌取材班)
※週刊朝日 2015年3月20日号より抜粋
